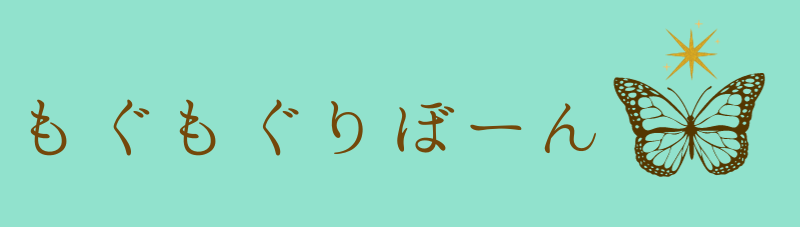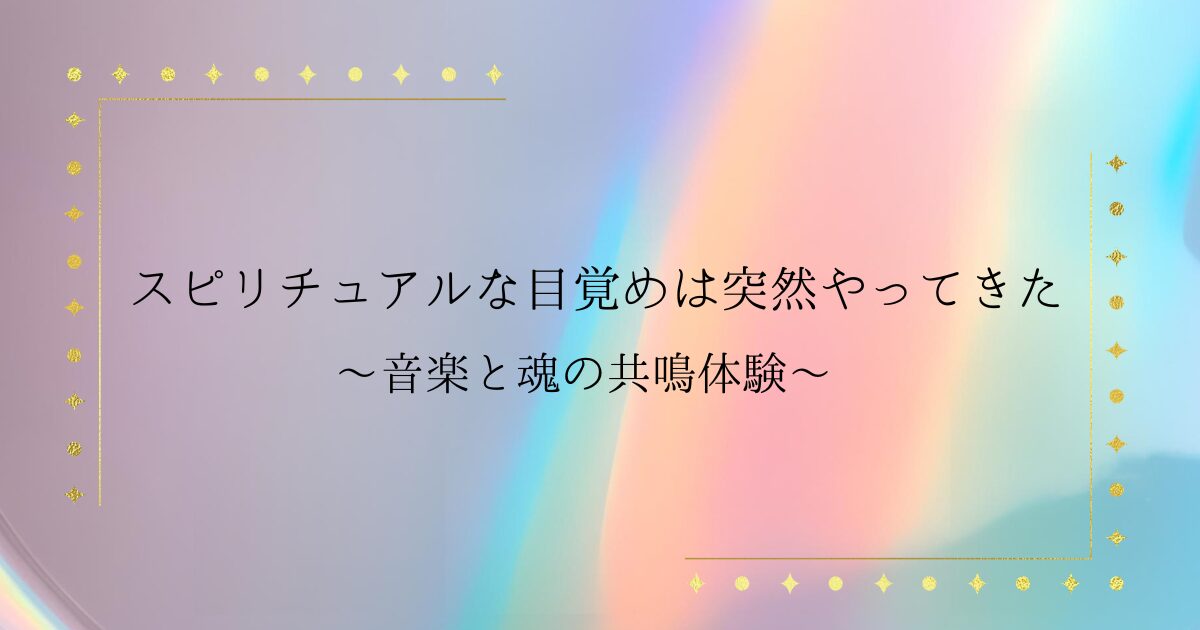目次
始まりは一瞬の感覚だった
あの日、
音楽を聴いていた私は、ふいに肉体の感覚を超え、
光の粒子となり、宇宙に溶けていくような感覚に包まれた。
魂が目覚め、
誰かの魂と共鳴するような、不思議で美しい体験だった。
「この感覚を、どうしても記しておきたい。」
その想いに駆られて、今こうして言葉を紡いでいる。
音楽と共に現れた、光の粒子のビジョン
それは本当に突然のことだった。
仕事を終え、疲れた体をソファーに預け、
イヤフォンからお気に入りの音楽を流していた午後。
外は暖かく、部屋の中は少しひんやり。
窓から入る柔らかい風が心地よく、心身ともに緩んでいた。
やがて、まぶたの裏に光の粒子が現れた。
それはピンクと青、二つの光だった。
光はさらさらと流れるように動き、柔らかく輝いていた。
ふと気づくと、私はその青い光そのものになっていた。
イヤフォンから聞こえる音楽に合わせ、光が優しく波打つ。
ピンクの光は、その音楽の振動そのものだった。
まるで引き合うように、二つの光が少しずつ近づいていく。
そして接した刹那、二つはまばゆい白い光となって弾けた。
私は”自由と喜び”という感覚そのものになった
白い光となった私は、こんなことを思っていた。
「制限がない(肉体がない)って、なんて自由なんだろう!」
「なんて軽やかで、心地良いのだろう!」
「嬉しい!楽しい!ワクワクする!」
「この私でどこまで拡大できるか、試してみたい!」と。
同時に、言葉では形容し難い圧倒的な感覚が、体中を駆け巡る。
それはまるで、全身全霊で、この喜びを宇宙中に示したがっているかのようだった。
私はその時、自由と喜びという”感覚そのもの”として存在していたのだと思う。
そして、この喜びを表現するかの如く、光である私は、宇宙の果てをめざして急速に拡大していく。
無限にきらめく星々を、銀河を、すべてを包み込みながら。
まるで私が拡大するのと同時に、宇宙も拡大してるかのようだった。
宇宙の果てが無いことに気づいたとき、恐れが生まれた
けれどある瞬間、はたと気づいた。
『どれだけ広がっても、宇宙の果てには辿りつかない』ということに。
最初は歓喜だけだった私の中に、一滴の墨のような感覚が混じる。
「……あれ?宇宙って果てがないの?どうしよう…。ちゃんと戻れるのだろうか?」
「怖い……!」
その“恐れ”が生じた瞬間、
私はパッと目を覚ましたのと同時に、光の旅は終わったのだった。
肉体に戻ったあとも、魂の残像が静かに私の内側を揺らしていた
目が覚めたあと、しばらく呆然としていた。
「ここはどこだろう?」
「私は誰だろう?」
やがて、少しずつ記憶が蘇ってくる。
「ここは地球で、私はソファに横たわって、音楽を聴いていた…。」
一つひとつ思い出すことで、ようやく現実に戻ってくることができた。
どれくらいの時間が経っていたのかはわからない。
数分?いや、何十分?
もしかしたら、刹那のような一瞬の出来事だったのかもしれない。
それを知る術がないことが、少し残念だった。
でもただ一つ、はっきりしていることがある。
あの鮮烈で圧倒的な『制限のない自由と喜びの感覚』が、今もなお胸に生々しく刻み込まれていたことだ。
魂が歓喜した”ダンス”は、永遠に消えない
私は初めて、
「制限のない自由」が、これほどまでに甘美で、心躍るものなのか…と驚愕した。
同時に「こんなに嬉しいの!楽しいの!この私を見て!」と、まるで無邪気な子どものような光の私がそこには居た。
あんなにも素直で純粋な感覚は久しぶりだった。
歓喜に震え、爆ぜて、弾ける姿。
あれはきっと『魂の歓喜のダンス』に違いない。
これはもう消えるはずがない。
一生どころか、たぶん永遠に忘れられないだろう、と思った。
この体験が意味することはまだわからない。でも確かなことがある
私に起きたこの共鳴体験の意味は正直わからない。日常は相変わらず続いている。
けれど、私の中に残った感覚は今なお息づいていて、それは間違いなく私の実体験であり、私の真実だ。
ふと、『あの自由は、もしかしたら肉体を脱いだ後に体験するものかもしれないな』と思った。本当にそうなのかはわからないけど。
制限のない自由はエクスタシーそのものだった。
「こんなにエクスタシーなら、そりゃ魂も歓喜するよね」と、心から納得した。
また、いつか。
あの光の自分と出会える日が来たら――。
そう願わずにはいられないほど、あの光景が、感覚が、瞼の裏に、体に、焼き付いて離れない。
光の自分と出会って、私は”本当の美しさ”に気づいた
まばゆく光る光の私は、とても美しかった。「光の私って、あんなに綺麗だったんだ…」と気付いて、なんだか泣けた。
私もあなたも、全てが光だ。
生きとし生ける全てがきっと、本当はこんなに美しい光なんだろうな。
だって、光である私の片鱗に触れただけで、この感動なのだから。
全貌に触れたら一体何を感じるのだろうか?私の小さなエゴでは到底想像もつかない。
「ああ、どうやら私は、とんでもないものを見てしまったようだ。」
突然訪れた体験で興奮冷めやらぬ私をなだめるように、午後の柔らかい風が、私の頬を優しく撫でていったのだった。